|
作者 たきねきょうこ
|
|
ページ 1 of 2  今年は、暖かい日が続くかと思えば、急に東山からの冷たい風と寒波が風花を舞躍らせ、襟もとをゆるめたり、手をかじかませたりのせわしなさ。 今年は、暖かい日が続くかと思えば、急に東山からの冷たい風と寒波が風花を舞躍らせ、襟もとをゆるめたり、手をかじかませたりのせわしなさ。
ご近所の侘助椿も寒さに白玉色の花首をかしげながら、次の小さな蕾をいつ開こうかと、思案げな様子。
それでも窓から差し込む日差しは、ほんの少しずつ身の丈の短さを増し、日の出の早さにあいまって、日の入りもこころもち、ゆるやかに暮れていくよう。
暦の上ではもう立春。その前の夜、豆に鬼が追われる節分のことを、京都では少し前まで「お年越し」と呼び慣わしてきました。
昔、中国の暦の上では、一年を二十四等分してその節目(ふしめ)の日を時節の分かれ目=節分と考え、色々な行事を執り行い、お祝い事を催してきました。
そして特にその中で、冬至から数えて四十五日目にあたる立春を一年の始まりの日、「立春正月」(りっしゅんしょうがつ)と定め、その前夜を「年越し」と呼んで逝く年の厄を祓い、来る年のさいわいを祈りました。
このお年越しの夜、祓われる「厄」は、実際には疫病であったり災厄であったり、冬の寒気そのものであったりするのですが、次第に「人に災いをもたらす、日ごろは隠れている異能のものたち」と考えられ、実体を伴い始めました。
これが節分につきもの「鬼」の由来で、「隠」(おに)とも書きあらわされて、災厄の象徴として、節分の厄払いの格好の「悪役」に据えつけられていきました。
また鬼は、陰陽五行説(いんようごぎょうせつ)によると、北東の方向=鬼門(きもん)に住んでいると考えられていたことから、魔物や災いから都を守るべく、京都の北東にあたる比叡山には地主神を祀る日吉大社(ひよしたいしゃ)と、鎮護国家を祈願して壮大な延暦寺(えんりゃくじ)が創建されました。
また東北を十二支であらわすと、丑寅(うしとら)の方向にあたることから、鬼にはその両方の特徴である、牛のような角と虎のような牙、そして腰には虎の皮のふんどしという、私たちにも馴染みの深いあの鬼独特のイメージが、次第に形作られていったようです。
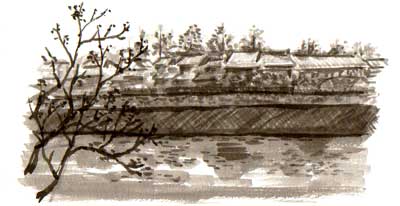
そしてその強面(こわもて)の鬼たちが投げつけられ、追われていくのが「煎り豆」(いりまめ)。豆は「魔目」や「魔滅」に通じるとされ、豆をまく慣習は室町時代にはじまったといわれています。
この煎り豆、きれいに洗い上げて水気をきった大豆を、焙烙(ほうらく)と呼ばれる素焼きの浅い炒り器で、少しずつほろほろと薄皮が割れ、香ばしく焦げ目がつくまで煎り上げたもの。少し冷ましてから、小半(こなから=二合五尺)の枡(ます)に山のように盛り上げて、神棚にお供えします。夕方、下げさせてもらったお豆さんを、翌日の立春からはじまる新しい年の分も含めて、自分の歳の数よりひとつ多くを、一握りでつかめると験(げん=縁起)が良いといわれていましたっけ。
 昔、大喜びで、福袋ならぬ腹袋へと祖母の煎り豆の分まで、せっせと片付けを手伝っていた孫娘も、今では、自分の歳の数を噛みくだすのが、少ししんどいお年頃になってきたような。 昔、大喜びで、福袋ならぬ腹袋へと祖母の煎り豆の分まで、せっせと片付けを手伝っていた孫娘も、今では、自分の歳の数を噛みくだすのが、少ししんどいお年頃になってきたような。
その後は、一番のお楽しみの豆まき。「福は内、鬼は外」と唱えながら、豆をまき終わった戸口や窓をすぐにピシャリと閉めていきます。これは一度追い出した鬼が、家の中へ戻ってくるのを防ぐためなのだそう。いつもならお行儀が悪いと叱られるほどの大きな音を立てながら、ガラス戸や障子を思いっきり締め切っていくことの爽快さを、母は後年、さも楽しそうに話してくれましたっけ。
<< 最初 < 戻る 1 2 次へ > 最後 >>
|



 今年は、暖かい日が続くかと思えば、急に東山からの冷たい風と寒波が風花を舞躍らせ、襟もとをゆるめたり、手をかじかませたりのせわしなさ。
今年は、暖かい日が続くかと思えば、急に東山からの冷たい風と寒波が風花を舞躍らせ、襟もとをゆるめたり、手をかじかませたりのせわしなさ。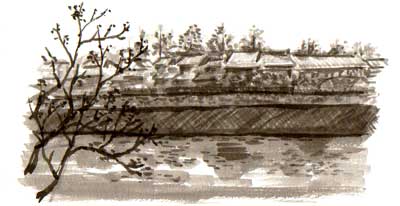
 昔、大喜びで、福袋ならぬ腹袋へと祖母の煎り豆の分まで、せっせと片付けを手伝っていた孫娘も、今では、自分の歳の数を噛みくだすのが、少ししんどいお年頃になってきたような。
昔、大喜びで、福袋ならぬ腹袋へと祖母の煎り豆の分まで、せっせと片付けを手伝っていた孫娘も、今では、自分の歳の数を噛みくだすのが、少ししんどいお年頃になってきたような。