 今年の夏の終わり際の、幕引きの手早いこと。
今年の夏の終わり際の、幕引きの手早いこと。
酷暑仕舞いのこしらえを、台風ごとに見事に納めこんで、気が付けばすだく虫達の音も声高に、あたりは秋の気配に満ちみちています。
帰っていった燕の巣跡を、軒のとゆ越しに覗き込む、秋の長雨も所在なげ。
この雨が上がったら、軒越しに、雲の切れ間から透き通った大きな月が、顔を覗かせてくれるでしょうか。
いにしえの昔より、月がもっとも美しいとされたこの季節、秋、長月。
白露を 玉になしたる九月(ながつき)の 有明の月夜 見れど飽かぬも
(万葉集 十-二二二九)
万葉のますらお人も、この季節、なりわいの手を止めて飽かぬとも尽きぬありようで、はるか天空の月影を見遣ったのでしょうか。
今も変わらずしららかな光を投げかけてくれる月は、古来より洋の東西を問わず、神聖なもの、また魔力を秘めた存在として、人々に崇められてきました。
ギリシャ神話の貞節な月の女神アルテミスは、また狩りの名手であり、嵐を自在に司るヘカテ神としての荒ぶる魔力をも同時に備え持っていました。今も欧米で盛大に祝われる万聖節(ハローウィン)は、この魔力を恐れ、崇めた古代の人々の信仰心が、後に伝わったキリスト教と習合して祭礼として定まっていったといわれています。
満月の夜、狼男は変身し、魔女は黒魔術の集会を開き、かぐや姫は、竹取の翁に見送られて、月光輝き渡る空高く、昇っていきます。
月には海水を満ち引きさせるだけでなく、私たちの身体の中に含まれる水分や、心それ自体をも惹きつける不思議な引力を、備えているように想えてなりません。
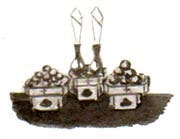 中秋の名月を賞する「お月見」は、中国で始まり、平安期に「観月の宴」として盛んに催されるようになり、やがて人々の歳時記に根付いていったもの。
中秋の名月を賞する「お月見」は、中国で始まり、平安期に「観月の宴」として盛んに催されるようになり、やがて人々の歳時記に根付いていったもの。
古くは「月夜見」(つくよみ)とも呼ばれ、神代紀には、月読尊(つくよみのみこと)として、月を男神として崇められており、また月自身をも月読男(つくよみおとこ)と擬人化して、神聖視されていたようです。 西洋では女神として、また、私たちの国では男神として月がお祀りされているのも、面白い逆説ですが、月を崇め憧れる想いは、いずれも同じこと。
お月見の元来のおこりも、中秋の美しい名月に惹き寄せられた人々の畏怖の心が、自然に儀式化され、慣習化していったのではないでしょうか。
京都の古いお家などでは、今も旧暦八月十五日の中秋の宵になると、お供え台の上に、萩やすすきが生け込まれ、対の御神酒がしつらえられて、三宝にはお団子とこいもが、その年の月の数(通年は十二個、閏年は十三個)だけきれいに積み上げて、お供えされます。
おさがりのお団子とこいもを、翌日の白味噌仕立てのお汁にしていただくのが、お月見の美味しいお楽しみの締めくくり。
折々の季節の取り決めことを、生真面目に受け継いできた人々の質素で風雅な暮らしむきが、湯気立つおなべの向こうから、かぎろい立ってくるようです。
 またこの日、月明かりに美しく彩られる社寺のあちらこちらで、観月の行事が催されます。平安時代以来、月の名所として名高い右京区の大覚寺では、前日の待宵(まつよい)と併せて二日間にわたって、観月の夕べが行われ、多くの風流人でにぎわい立ちます。
またこの日、月明かりに美しく彩られる社寺のあちらこちらで、観月の行事が催されます。平安時代以来、月の名所として名高い右京区の大覚寺では、前日の待宵(まつよい)と併せて二日間にわたって、観月の夕べが行われ、多くの風流人でにぎわい立ちます。
水面が夕闇に染め付けられる午後五時半頃、大沢池には龍頭船(りゅうとうせん)や、鷁首船(げきしゅせん)など4隻の観月船が、天神の島影近くまで漕ぎ出されます。また、境内の五大堂では、満月法会が営まれ、献花に彩られた月光菩薩も、月の出を待つ人々のささやき声と琴や尺八の樂音に、密やかに耳を傾けていらっしゃるようです。
この他にも左京区の下鴨神社では、名月管弦祭が催され、平安装束を身に着けた楽人の、舞楽が、管弦の音に合わせて、奉納されます。また、観月の名所とされる嵐山や広沢池、また宇治川縁などのそこここでも、名月を愛でる行事が営まれ、お月見を楽しむ人々が集いあいます。
天神さんの名で親しまれている、上京区の北野天満宮では、芋茎(ずいき)と栗、里芋などをお供えすることから芋名月と呼ばれる名月祭が催されます。ちなみに、同じアジアの台湾では、儀式用に収穫したタロイモに、すすきをさして、魔よけにするのだかとか。
実りの恵みを喜び、自然の恵みを尊ぶいにしえ人の、素朴な感謝の祈りも、また、月への信仰心の礎のように想われます。
そして、お月見台の上のすすきのかたわらで、可憐な花を揺らして、たわむ萩の花。
もう少し秋が深まりお彼岸になると、決まっていただく甘いおはぎは、あの小豆のつぶつぶが、萩の花に似ているからこう呼ぶのだとか。そういえば、また、形がぼたんの花に似ていることから、春のお彼岸にいただくときは、ぼた餅というのだそう。
季節によっての呼び名はいざ知らず、もち米をまぜたご飯を軽くついて、手ごろな大きさに丸め、あんこや黄粉でくるんで、せいろで蒸し上げたこのおはぎは、少し前まではどこのお家でもお彼岸に作られ、お供えのお下がりも待ち遠しくよばれたもの。
小豆や黄粉だけでなく黒ごまや青のりでまぶされた色とりどりのおはぎを、おまんやさんで買うようになった今も、小豆の粒を幾つもくっつけながら、おはぎをほうばる息子の姿は、幼かった頃の私のうつし絵そのもの。
そして、やがては綿々と引き継がれてきたつつましい慣わしごとのなかに、ありきたりのすこやかさを願う、埋み火のような祈りが熾り続けていることに気付いて、その重さにたじろぐこともあるのでしょうか。・・・この小さな黄粉だらけの掌は、いつか。
たわいない子供たちのおだやかな暮らしが、今年も、そしてこれからも、すこやかに続いていきますように。
燕は、来年もあの軒下の巣穴で、つつがなく雛鳥たちをはぐくむことができますように。
そして、中秋の大きな丸い月がその永々とした営みを見守りながら、今年も美しく天空に照り映えますように。